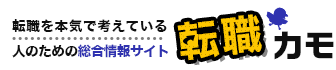医大生を6年、国家試験合格から2年の研修医…そしてさらに大学院で博士号取得…キャリアを積むには早いうちから目標を決めるのが大事。
でも、実際にはいつでも転機があったり、自分の性格と照らし合わせて「執刀がいい」「臨床が向いている」と考えながら6年間過ごす方もいらっしゃるのではないでしょうか?
都市部の病院で研修するのがいいのか、それとも地方の総合診療科がいいのか…様々な選択肢が医師にはあるはず。その中には研究医の道もあります。
そればかりではありません。ここでは研究医の様々な道もご紹介していきます。
そもそも臨床医・研究医とは
臨床医とは一般的に私たちの街の病院にいるお医師さんのことを言います。
病院に診察に来た患者へ治療や予防に関する指導を行っています。
研究医とは、大学や研究機関などで医学研究をする医師のことです。
医療の最前線に立ち、未だ治療法が確立されていない病気の治療方法を新たに探索するなど、医学の進歩に貢献する役割を担っています。
臨床医と研究医、どこで働いているの?
厚生労働省の調べでは平成30年(2018年)12月31日現在、日本には327,210人の医師が在籍しています。
出典:平成30年(2018年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 | 厚生労働省(PDF)
大まかな内訳は以下のようになります。
| 医療施設の従事者 | 311,963名 |
|---|---|
| 介護老人保健施設の従事者 | 3,388名 |
| 介護医療院の従事者 | 55名 |
| 医療施設・介護老人保健施設・介護医療院以外の従事者 | 9,331名 |
| その他業務の従事者・無職の方 | 2,448名 |
上表を見ると医療施設の従事者、いわゆる臨床医(病院やクリニック、大学病院などの医療施設勤務者)が311,963名と割合的に95.3%が医療機関で勤務しているということになります。
では研修医はどこにいるのでしょうか?
表の「医療施設・介護老人保健施設・介護医療院以外の従事者(9,331名)」がおそらく研修医に当たると思います。
9,331名の内訳は、
- 医育機関の非臨床系大学院生として…730名
- 医育機関の非臨床系医師として…3,019名
- 医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者…1,476名
- 行政機関・産業医・保健衛生業務の従事者…4,106名
となっていて研修医の割合は3~4%となっています。
圧倒的に臨床医の方が多いということがわかりますね。
では研究医は具体的にどんなことをしているのかを次の段落で解説いたします。
具体的に研究医にはどんな道があるの?
研究医というと医科大学で教授・准教授・講師・助教といった研究者をイメージできます。
英語での論文に汗を流し、ひたすら業績を積み重ねる基礎研究ですが、有名なのはiPS細胞研究でノーベル賞受賞の山中伸弥京大教授です。
山中教授はもともと整形外科の臨床医でしたが、挫折を味わい再び大学院に入りなおして研究医として成功します。
そのほかには、
- 製薬会社内医師
- 国家公務員医師(厚生労働省技官)
- 法医学者(警察関連)
- 防衛医官(防衛省)
など、様々な分野で研究医のフィールドが広がっています。
また、最近では研究医の中には収まらない経営者としての一面を見せる医師も。
臨床医から研究医になるにはハードルが高い?
一旦臨床医として外の社会に出ても「自分は臨床には向いていない…」という医師は意外にも多いのです。
誰もがコミュニケーションが達者なわけでもなし、外交的なわけでもなし。
ましては「興味のある研究テーマが出てきて、使命感でさえも出てきた」という方は研修医を目指したいはず。
では、臨床医として4年5年経って研究医になるのはハードルが高いのでしょうか。
結論から言うとそんなことはありません。
横浜市立大学大学院医学研究科のように臨床医をウェルカム!という大学は増えています。
臨床医兼研究医という道も実はメジャーになりつつあるのです。
臨床医から研究医への転身をする際の注意点
ただ、ここで忠告です。
臨床医から研究医への転身はあくまでも「二足の草鞋」。
10年先20年先の医学研究者として考えるなら、学生6年のうち4年目あたりで研究の道を選ばなければいけません。
なかなか踏ん切りがつかないなら、思い切って大学院の”基礎研究”に進みましょう。
人生やり直しはいつでも出来ます!
研究医から臨床医への転職は容易
一方で、多くの研究医が臨床医へと転身を図る道があります。
そこには積極的理由と消極的理由があるカモ。
積極的理由とは「キャリア形成」。
大学での研究もキャリアとして大きいけれど、やはり臨床医として現場で働くことへの希望も叶えたい。
研究医のすばらしさは何千万人という人の医療に役立つことですが、臨床医は目の前の患者を治す”実感”を味わえる…そういった理由での転職があります。
もちろん、30代の転身と50代の転身、60代の転身には迎えられるフィールドは全く違います。
が、臨床医としての仕事は数限りなく存在するのカモ。
もう一つが消極的理由。
大きな問題はやはり「人事」と「収入」。
6年、8年、10年…と大学内で過ごす中、やはり気になるのは安定した収入の確保。
ですが、医師全体では1,160万円程度(厚生労働省賃金構造基本統計調査より)。
中には2,000万円、3,000万円といった開業医にもお目にかかります。
やはり、安定した年収を取るなら臨床医の方が良い…ということになります。
関連記事:研究医から臨床医への転職をしっかりサポート「エムスリーキャリア」
 エムスリーキャリアの評判や口コミを検証!強みは常勤転職率が高い点
エムスリーキャリアの評判や口コミを検証!強みは常勤転職率が高い点
どんなタイプの人が臨床医に向いている?
臨床医に向いている方…もちろん臨床にも様々な選択肢がありますが、大事なことは「今持っているスキルで患者を救う」という想いを持っていること。
ただ、社会人入学で医学生、研修医、臨床医と過ごしている方は、場合によっては将来にわたってキャリアが短くなり、外科医ならば選手生命が短縮…というケースも考えられます。
どんなタイプの人が研究医に向いている?
臨床医と研究医…それぞれ人生の選択があります。
ただ、人それぞれの性格やタイプにあった選択肢が幸せの源泉です。
ではどんな人が研修医に向いているのか4つあるのでそれぞれ紹介していきます。
1.論理思考が極めて得意な方
では、研究医に向いているタイプは”論理思考”の持ち主であること。
自分の研究をうまく伝える能力(論文でよし!)のある方が大事です。
2.チームで仕事が出来る方
もう一つがポジションに分け隔てなくチームで仕事が出来る方です。
もちろん、教授は監督ですから、それ以外はみんなが選手という考え方ですね。
3.失敗を恐れない人
研究結果が自分の予想と違かったからといって、それを失敗と考える人は向いていません。
予想と違う=失敗ではなく、予想と異なるデータを見て「なぜ予想と違ったのか」を考え、その理由が解明できれば、「成功」になります。
失敗を恐れず、手探りで成功を手繰り寄せられる方が研修医に向いていると言えます。
4.臨床医にはなれない人
そして臨床医にはなれない人。
例えば緊急執刀は「目の前にある危機を救う」…
これは向いていないなあ…という方もいるでしょう。
研究医の方がじっくりと仕事が出来るという方は研究医を目指しましょう。
まとめ
臨床医と研究医の割合は、圧倒的に臨床医の方が多いのが現実です。
現在の研修医制度改革で、ますます研究畑に留まる方が少なくなりました。
ですが、研究医として名を挙げている医師は多く、そのフィールドも多彩です。
研修医として働くか、研究医として働くか…収入面の噂に惑わされず、ご自分の”選択肢”を信じて突き進んで下さい。